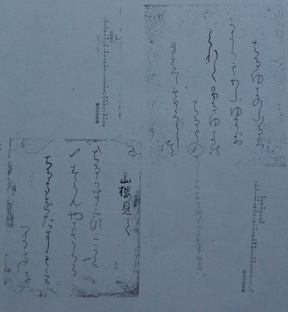
百人一首 7…33〜38
三三 ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ 紀友則(きのとものり)
【出典】
『古今和歌集』春・下・84
桜の花の散るをよめる 紀友則
久方の光のどけき春の日にしづこゝろなく花の散るらむ
【現代語訳】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
このように日の光がのどかにさしている春の日に、桜の花はおちついた心もなくはらはらと散ることよ。どうしてこうもあわただしく散るのかしら。
【鑑賞】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
「この歌は慌しく散る花が、のどかな春の心持を乱すのを咎めたものではあるが、さうしたぎこちない難詰の心は、ゆるやかに流れゆく『しらべ』の波にかくされてしまって、風なきに舞ふがごとくもかつ散る花をながめながら、霞の中をたゞよふ陽光に包まれて、爛熟した春を味ひつゝある歌人の心持がさながらに浮び出てゐる。もし仮に『など』といふやうな咎めの副詞がこの歌に用ひられてあるとしたらどうだろう。興味は頓に索然として、春なほ寒き心地にをののかざるを得ないであろう」(吉沢義則氏「貫之の考へてゐた和歌の本質について」)。野中春水氏の『新注小倉百人一首』に引用されているのだが、この歌の鑑賞として何より適切であると思う。
【語釈】
※しづこゝろなく花の散るらむ→「など(どうして)静心なく花の散るらむ(散るのだろうか)」の意に解す説と、「らむ」を連体形止めの余情表現と見て、「静心なく花の散っているだろうことよ」と解する説があるが、後者の場合、現在推量の「らむ」の用法から見て、現実に散る花を見ていないで、イメージしていることになる。
宿りせし花橘も枯れなくになどほととぎす声絶えぬらむ (古今集・夏・155・大江千里)
【他の秀歌選の友則歌】
公任『前十五番歌合』十三
夕されば佐保の川原の川霧に友まどはせる千鳥鳴くなり
※歌合→二首づつの組み合わせ。歌合せ形式の名残。
※前(さき)→再び十五番歌合が出来たので「前」「後」と呼ばれている。
公任『三十六人撰』五六・五七・五八
夕されば佐保の川原の川霧に友まどはせる千鳥鳴くなり
雪降れば木ごとに花ぞ咲きにけるいづれを梅と分きて折らまし
※木ごと→「木」と「こと」と梅を分けて読んでいる。
秋風に初雁が音ぞ聞こゆなる誰が玉章(たまづさ)を懸けて来つらむ
※玉章→手紙
※中国の漢の時代の蘇武の話で「幽閉されて帰れなくなり雁の足に手紙をつけて帰したという話を引用」している。
俊成『俊成三十六人歌合』二八・二九・三〇
夕されば蛍よりけに燃ゆれども光見ねばや人のつれなき
※けに→いっそう、激しく。
東路の小夜の中山なかなかに何しか人を思ひ初めけむ
※なかなかに→中途半端。
下にのみ恋ふれば苦し玉の緒の絶えて乱れむ人なとがめそ
※玉の緒→心。
後鳥羽院『時代不同歌合』九七・九九・一〇一
夕されば蛍よりけに燃ゆれども光見ねばや人のつれなき
東路の小夜の中山なかなかに何しか人を思ひ初めけむ
下にのみ恋ふれば苦し玉の緒の絶えて乱れむ人なとがそ
定家『百人秀歌』『百人一首』
ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ
【影響史】
「静心」→定家没後100年後まではよく引用されていた。200年後は出てなかったが拾遺愚集・212で再び出て来た
ことならば咲かずやはあらぬ桜花見る我さへに静心なし (古今集・春下・82・貫之)
春の日をいま幾日とも思はねば静心して花をやは見る (躬恒(みつね)集・406)
※躬恒は人の言い方をすぐ真似る特徴があった。自分自身が楽しむ。
もみぢ葉の風のまにまに散る時は見る人さへぞ静心なき (躬恒集・338)
桜花にほふを見つつ帰るには静心なきものにぞありける (兼輔集・12)
※にほふ→輝いている(視覚)
※兼輔→貫之のスポンサー。
いつとなく静心なき我が恋にさみだれにしもみだれそふらむ (敦忠集・67)
言ひそめぬ程はなかなかありにしを静心なき昨日今日かな (信明(さねあきら)集・123)
※信明→友則より50年後。
うつつにも静心なき君なれば夢にもかりと見えつるがうさ (元良親王集・125)
※かり→仮の姿。
秋近くなりゆく月の影見ればあやしく人ぞ静心なき (能宣(よしのぶ)集・303)
※能宣→970年位の人。
春は惜しほととぎすをば聞かまほし思ひわびぬる静心かな (元輔集・95)
来る夏と別るる春の中にゐて静心なき物をこそ思へ (重之集・70)
※重之→900年代後半の人。
吹く風の静心なき舟路にはさらばよと言ひし人ぞ恋しき (重之集・133)
この衣の色白妙になりぬとも静心ある毛衣にせよ (和泉式部集・431)
※和泉式部→1000年頃の人。紫式部より心もち前の人。
見るほどに散らば散りなむ梅の花静心なき思ひおこせじ (和泉式部続集・308)
物思へば静心なき世の中にのどかにも降る雨のうちかな (和泉式部続集・595)
いかにして静心なく散る花ののどけき春の色と見ゆらむ (拾遺愚集・212)
※静心→再び復活。
【紀友則】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
生没年未詳。延喜五、六年(905、6)の没か。宮内権少輔紀有朋(古今歌人)の息子。貫之の従兄。寛平九年(897)正月土佐掾、少内記をへて延喜四年(904)正月大内記となる。『寛平御時后宮歌合』に先だつ『寛平内裏菊合』に加わって以来、歌壇に活躍し、貫之・躬恒より先輩格にあった。『古今集』の撰者となったが、奏覧以前に没した。三十六歌仙の一人。家集に『友則集』がある。『古今集』に四十六首、『後撰集』以下の勅撰集に約二十首入集。
三四 誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに 藤原興風(ふぢはらのおきかぜ)
【出典】
『古今和歌集』雑上・909
(題しらず)
誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに
【現代語訳】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
私はだれを昔からの知りあいとしようかなあ。高砂の松のほかには、私と同じように年をとったものはないが、それも昔からの友ではないから、話し相手にならないし。
【鑑賞】
昔の友人がみんな死んでしまって、孤独を痛切に身に感じている老人の嘆きの声をよんだもの。『古今集』に並んで見える「かくしつつ世をやつくさむ高砂の尾上にたてる松ならなくに」の歌をもとによんだのであろうが、興風の歌は人々に強い感動を与えたと見え、貫之も「いたづらに世にふる物と高砂の松も我をや友と見るらん」(拾遺集・雑上)とよんでいる。この歌は公任の『三十六人撰』にも選ばれていて、興風の代表作としての評価は以後動いてはいない。「定家は、あの多感な魂に老愁の苦さを吸いつくした人である。……この歌の中に、彼は自分の心の姿を見ているのかも知れない」という石田吉貞氏の見解はいかにもと首肯される。
【語釈】
※誰をかも知る人にせむ→「誰」は「たれ」と読む。「だれ」になったのは、明治まで「たれ」と清音であった。「か」は疑問の係助詞。「も」は余情詠嘆の気持ち。「誰を我が知己としようか。知っている人なんて誰もいないんだなあ…」という気持ち。
高砂の松も昔の友ならなくに→【参考1】【参考2】参照。
【参考1】
「高砂」は固有名詞か普通名詞か
※普通名詞の例
『後撰集』春中・50
花山にて、道俗、酒らたうべける折に 素性法師
山守は言はば言はなむ高砂の尾上の桜折りてかざさむ
※花山→花山の元慶寺・父僧正遍昭ゆかりの寺。
※固有名詞の例
『後拾遺集』雑三・985
身のいたづらになりはてぬることを思ひなげきて、播磨にたびたびかよひ侍りけめに、高砂の松を見て
藤原義定(ふじわらのりさだ)
我のみと思ひこしかど高砂の尾上の松もまだ立てりけり
『古今集』仮名序
しかあるのみならず、さざれ石にたとへ、筑波山にかけて君を願ひ、喜び身に過ぎ、楽しび心にあまり、富士のけぶりによそへて人を恋ひ、松虫の音(ね)に友を偲び、高砂、住の江の松も相生のやうにおぼえ、男山の昔を思ひ出でて、女郎花のひと時をくねるにも、歌を言ひてぞなぐさめける。
【参考2】 「松も昔の友」
※『古今集』雑上905〜909
(題しらず) (よみ人しらず)
我見てもひさしくなりぬ住の江の岸の姫松幾代へぬらむ
※姫松→小さい松。 ※幾代へぬらむ→長い時間を表す。
住吉の岸の姫松人ならば幾代か経しと問はましものを
※住吉の岸の姫松→何代も生えている。
梓弓磯辺の小松誰が代にかよろづ代かねて種を蒔きけむ
※かねて→あらかじめ。
かくしつつ世をや尽くさむ高砂の尾上に立てる松ならなくに
誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに
*阿波国文庫本『伊勢物語』
昔、みかど、住吉にみゆきしたまひけるに、よみて奉らせ給ひける。
我見てもひさしくなりぬ住の江の岸の姫松幾代へぬらむ
御神あらはれ給ひて、
むつましと君は知らずや瑞垣の久しき代よりいはひそめてき
※いはひ→健康を守る。
このことを聞きて、在原業平、住吉にまうでたりけるついでに、よみたりける。
住吉の岸の姫松人ならば幾代か経しと問はましものを
よめるに、翁のなりあゆしき、出でゐて、めでて、返し、
衣だに二つありせばあかはだの山に一重は貸さましものを
※御神あらはれ給ひて→松という霊的なもの依代(よりしろ)にする(門松など) ※あらはれ→現形(げんぎょう)
※山に一重は貸さましものを→松の緑は一つしかない。
【参考3】 『古今集』の歎老歌
題しらず よみ人しらず
886 いそのかみふるからをののもとがしは本の心はわすられなくに
887 いにしへの野中のし水ぬるけれど本の心をしる人ぞくむ
888 いにしへのしづのをだまきいやしきもよきもさかりは有りしものなり
※をだまき→糸まき。
889 今こそあれ我も昔はをとこ山さかゆく時も有りこしものを
890 世中にふりぬる物はつのくにのながらのはしと我となりけり
891 ささのはにふりつむ雪のうれをおもみ本くだちゆくわがさかりはも
※うれを→梢。
892 おほあらきのもりのした草おい(ひ)ぬれば駒もすさめずかる人もなし
又は、さくらあさのをふのしたくさおいぬれば
893 かぞふればとまらぬ物を年といひてことしはいたくおいぞしにける
※年→「とく」の終止形。早く。
894 おしてるやなにはのみつにやくしほのからくも我はおいにけるかな
※おしてるや→「なには」の枕詞
又は、おほとものみつのはまべに
895 おいらくのこむとしりせぱかどさしてなしとこたへてあはざらましを
このみつの歌は、昔ありけるみたりのおきなのよめるとなむ
896 さかさまに年もゆかなむとりもあへずすぐるよはひやともにかへると
897 とりとむる物にしあらねば年月をあはれあなうとすぐしつるかな
※あはれあなう→悲しい、嫌だ。
898 とどめあへずむべもとしとはいはれけりしかもつれなくすぐるよはひか
※むべも→なるほど。 ※とし→一年。
899 鏡山いざ立ちよりて見てゆかむ年へぬる身はおいやしぬると
この歌は、ある人のいはく、おほとものくろぬしがなり(滋賀県の人)
業平朝臣のははのみこ長岡にすみ侍りける時に、なりひら宮づかへすとて時時もえまかりとぶらはず侍りければ、しはすばかりにははのみこのもとよりとみの事とてふみをもてまうできたり、あけて見ればことばはなくてありけるうた
※時時→あの時・この時。 ※とみ→急。
900 老いぬればさらぬ別もありといへばいよいよ見まくほしき君かな
※さらぬ別→死別。 ※みまくほしき→会いたい。
返し なりひらの朝臣
901 世中にさらぬ別のなくもがな千世もとなげく人のこのため
※なげく→祈る。 ※人のこのため→自分を含めた人間の子供。
寛平御時きさいの宮の歌合のうた 在原むねやな(業平の子供)
902 白雪のやへふりしけるかへる山かへるがへるもおいにけるかな
おなじ御時のうへのさぶらひにてをのこどもにおほみきたまひておほみあそびありけるついでにつかうまつれる
※おなじ御時→宇多天皇。 ※おほみあそび→音楽。
としゆきの朝臣
903 おいぬとてなどかわが身をせめぎけむおいずはけふにあはましものか
題しらず よみ人しらず
904 ちはやぶる宇治の橋守なれをしぞあはれとは思ふ年のへぬれば
※宇治の橋守→神のように扱われている人。
905 我見てもひさしく成りぬ住の江の岸の姫松いくよへぬらむ
906 住吉の岸のひめ松人ならばいく世かへしととはましものを
907 梓弓いそべのこ松たが世にかよろづ世かねてたねをまきけむ
この歌は、ある人のいはく、柿本人麿がなり
908 かくしつつ世をやつくさむ高砂のをのへにたてる松ならなくに
藤原おきかぜ
909 誰をかもしる人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに
※905.906.907.908.909→松を通じて老いを詠んでいる。
【藤原興風】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
生没年未詳。参議浜成(歌経標式の著者)の曽孫。道成の息子。昌泰三年(900)正月、相模掾。治部少丞、上野権大掾をへて、延喜十四年(914)四月下総権大掾に至る。『寛平御時后宮歌合』以下にその作が見え、宇多天皇の歌壇において活躍した。屏風歌の詠もあって『古今集』撰者時代の有力歌人である。管絃にすぐれ、弾琴の師ともなった(古今集目録)。三十六歌仙の一人。家集に『興風集』(他撰)がある。『古今集』に十七首、『後撰集』以下の勅撰集に二十一首入集。
三五 人はいさこゝろもしらずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける 紀貫之(きのつらゆき)
【出典】
『古今和歌集』春・上・四二
初瀬にまうづるごとに宿りける人の家に、ひさしく宿らで、程へて後に至れりければ、かの家の主「かく定かになむ宿りはある」と言ひ出して侍りければ、そこに立てりける梅の花を折りてよめる。
貫之
人はいさ心もしらずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける
【現代語訳】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
あなたの方は、さあどうだか、お気持ちも知られないけれど、さすがこの旧都奈良では、花の方だけは、昔のままの香で咲き匂っていますね。
【鑑賞】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
作歌事情は『古今集』の詞書に示すように、貫之が昔なじみの女とかわした当意即妙の挨拶の歌だが、定家はこの歌に、美しい春景色の旧都を背景としてかわされた回想的・詠嘆的なよみぶりを余情に富んだものと見たのであろう。「哥の心たぐみに、たけを(お)よびがたく、詞(ことば)強く姿おもしろき様をこのみて余情妖艶の躰をよまず」(近代秀歌)と貫之を評した定家が、あえて余情の歌を選びとったのである。公任の『三十六人撰』十首の中にもなく、俊成がすっかり選びかえた三首の中にもなく、定家が『秀歌躰大略』の秀歌例にはじめて取りあげて高く評価した歌といえよう。公任は「桜散る木の下風は寒からで空に知られぬ雪ぞふりける」を代表作とみていたのである。
【語釈】
※初瀬にまうづるごとに→長谷寺に参詣する度に。『日本書紀に「泊瀬」と書くように、「ハクセ」から、「ハツセ」、「ハセ」と変化したのであろう。観音信仰の霊場。
※かの家の主→後「言ひ出だして侍りければ」の「言ひだす」中にいる女から外にいる男にことばをかけること。
※いさ→「ず」などの打消の辞をともなって「さあ……ない」の意。「いざ」ではない。
※ふるさと→古い里。昔なじみの里。
【影響】
『古今集』『貫之集』以降、不思議に他の文献に引かれることがなかったが、定家の『二四代集』、『詠歌大概』『百人一首』『百人秀歌』などに引かれて有名になった。歌物語的雰囲気、絵画的雰囲気が定家に好まれたのであろう。
定家以後のことだが、『源平盛衰記(じょうすいき)』巻十「丹波少将上洛事」に、
殿ハ、京中ニモ限ズ、所々ニ山庄多持給ヘリ。其中ニ鳥羽ノ田中殿ノ山庄ヲバ、殊ニ執(しっし)思給テ、私ニ洲浜殿トゾ申ケル。少将ハ日ヲモ暮サンタメ、父ノ遺跡モナツカシクテ見巡給ケレバ屋敷ハ昔ニ替ラネドモ、蔀格子モナカリケリ。築地崩テ覆朽、門傾テ扉倒(たふる)。庭ニハ千種生茂、人跡絶テ道塞、蘿門乱テ地ニ交リ、唐垣破テ絡石ハヘリ。檐ニハ垣衣、苅萱生カハシ、月漏トテ葺ネドモね板間マバラニ成ニケリ。少将アノ屋コノ屋ニ伝ツヽ。大納言ハコヽニコソ御坐(おはせ)シカ、彼(かしこ)ニコソ立給シカナド思ツヾケ給テモ、哀ノミコソ増(まさり)ケレ。何事ニ付テモ皆昔ニ替(かはり)タレドモ、此(ころ)ハ三月ノ中ノ六日ノ事ナレバ、秋山ノ梢ノ花所々ニ散残(ちりのこり)、楊梅桃李ノ匂モ、折知顔ニ色衰、百囀ノ鶯モ、時シアレバ声己ニ老タリ。少将悲(かなしみ)ノアマリニ木ノ本ニ立ヨリ、古キ詩ヲ詠ジ給ヒケリ。
桃李不言春幾暮 煙霞無跡昔誰栖
ト。又思ツヾケ給フ。
人ハイサ心モシラズ故郷(ふるさと)ハ花ぞムカシノ香ニヽホヒケル
イツシカ田舎ニ引替テ、入相ノ野寺ノ鐘ノ音、今日モ暮ヌト打響ク。彼(かの)遺愛寺ノ辺ノ草庵ニ似タリケリ。王昭君ガ胡国ノ夷(えびす)ニ囚レテ後、其跡角(かく)ヤ有ケント思ヤラレテ哀也。姑射山(こやさん)仙洞ノ池ノ汀ヲ望バ、春風波ニ諍テ、紫鴛白鴎逍遥セリ。興ゼシ人ノ恋サニ、イトヾ涙ぞコボレケル。
【紀貫之】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
生年未詳ー天慶八年(945)。貞観十四年(872)出生か。紀望行の息子。越前権少掾・大内記・加賀介・美濃介・土佐守など下級官を歴任、従五位上木工権頭に至る。延喜初年より歌合・屏風歌の作者となる。兼輔邸にしばしば出入りする。『古今集』の撰進を受け、友則没後は中心となり『古今集』を完成。仮名序に歌論を示し、『土佐日記』『新撰和歌』の著をなした。家集に『貫之集』がある。『古今集』に百二首、総じて勅撰集入集約四百五十二首、定家についで多い。
三十六 夏の夜はまだ宵ながら明ぬるを雲のいづくに月宿るらむ 清原深養父(きよはらのふかやぶ)
【出典】
『古今和歌集』夏・166
月のおもしろかりける夜、あかつきがたによめる
深養父
夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづこに月宿るらむ
【現代語訳】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
短い夏の夜は、まだ宵のくちと思っているうちに明けてしまったが、とても西の山まで行きつくひまはなさそうだからあの楽しい月は雲のどこにやどっているのだろう。
【鑑賞】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
誇張と機知にみちた古今調の代表作で、『新撰和歌』や『古今六帖』巻一にも取られ、当時はみとられた歌であったが、歌人深養父が公任の『三十六人撰』にもれたことも原因して、平安時代を通じては、たいして名歌の扱いを受けなかったようである。それが、平安時代末期になると、俊成の『古来風躰抄』に選ばれ、清輔の『袋草子』にも深養父が三十六歌仙に洩れていることに不審を持つなど価値が見直されてきた。特にこの歌は新古今時代に多くの類歌が生まれたが、「夏の夜は雲のいづくに宿るともわが面影に月は残さむ」(秋篠月清集)などに見られるように、雲のかなたに惜しまれつつ姿を隠している月を思いうかべて余情を感じていたように思われる。
【語釈】
※月のおもしろかりける→「おもしろし」は、見て心を楽しませることができることをいう。
※あかつきがた→夜を大別すると、「宵」→「夜半(よわ)」→「暁」と続く。「あかつき」は夜の最後の時間帯。限りなく朝に近い夜。『萬葉集』では「あかとは」(夜が明ける時)と言い、「五更」「鶏鳴」という字をあてる。「五更」は午前3時から5時の間、「鶏鳴」は一番鶏が鳴くまだ暗い時刻のことであろう。宵から直接暁になった感じで、夜半がなかったと言っているのである。
※雲のいづくに→定家書写の貞応二年本や嘉禄二年本では「雲のいづこに」とあるが、父俊成の昭和切には「雲のいづくに」とある。同じ意だが、「いづくに」の方が古雅な感じである。【影響】参照。
【影響】
帰る雁雲のいづくになりぬらむ常世(とこよ)の方の春のあけぼの (良経 秋篠月清集606)
夏の世は雲のいづくに宿るともわが面影に月は残さむ (良経 秋篠月清集1092)
過ぎぬなり有明の空のほととぎす雲のいづくに声残るらむ (家隆 壬二集1655)
澄む月の光は霜とさゆれどもまだ宵ながら有明の空 (家隆 壬二集320)
折しもあれ雲のいづくに入る月の空さへ惜しきしののの道 (定家 拾遺愚草1632)
宵ながら雲のいづこと惜しまれし月を長しと恋ひつつぞ寝る (定家 拾遺愚草2553)
山路ゆく雲のいづこの旅枕臥すほどもなく月ぞ明けゆく (定家 拾遺愚草1177)
【参考】
「升色紙」について
『深養父』の断簡。伝藤原行成筆。しかし、十一世紀後半の書写。
『寸松庵色紙』『継色紙』とともに三色紙と称されている。
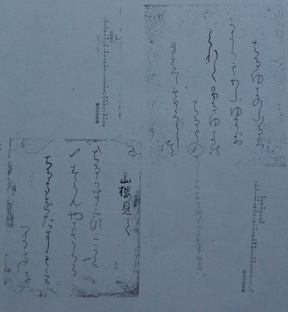
【清原深養父】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
生没年未詳。豊前介房則の息子(古今集目録)。元輔の祖父、清少納言の曾祖父に当たる。延喜八年(908)内匠允、同八年従五位下。晩年洛北市原野に補陀落寺を建立したという(『拾芥抄』、『平家物語』大原御幸)。琴にすぐれ兼輔邸に出入りしていた(後撰集・夏)。『寛平御時后宮歌合』に見え、『古今集』に十七首入集する。有力歌人であるが、屏風歌などの作が見えない。家集に『深養父集』がある。『古今集』の資料に提供したという説もある。
三七 白露に風の吹きしく秋の野はつらぬきとめぬ玉ぞ散りける 分屋朝康(ふんやのあさやす)
【出典】
『後撰和歌集』秋中・308
(延喜御時、歌召しければ)
文屋朝康
白露に風の吹きしく秋の野はつらぬきとめぬ玉ぞ散りける
← 実景 →← 見立て →
【現代語訳】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
草の葉の上にいっぱいたまっている白露に、風が吹きしきる秋の野は、ちょうど緒(糸)に貫きとめてない玉がはらはらと散り乱れるようで、いかにも美しい光景だことよ。
【鑑賞】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
白露の美しく光落ちるのを、写実的に描かないで、「貫きとめぬ玉」と比喩を用いて表現するところは、古今調であり、同じ朝康の「秋の野におく白露は玉なれやつらぬきかくるくもの糸すぢ」(古今集・秋上)や忠岑の「秋の野におく白露をけさ見れば玉やしけるとおどろかれつつ」(後撰集・秋中)と同巧同想の歌であるが、定家が特にこの歌を高く評価して『自筆本近代秀歌』『秀歌躰大略』『八代集秀逸』に選び入れているのは、寂しい秋の野分のながめの中に、白露の美しさを見いだしたところにひかれたのであろう。『龍吟明訣抄所引冷泉家伝抄』に、「唯此歌は花をもつぱらによみて実すくなし。然れ共、定家卿あまり風情の面白きゆへ(ゑ)入(いれ)られたるよしなり」という。
【語釈】
※文屋朝康→文屋康秀の子。定家は貞応(1222-24)頃は「文屋」と書いていたが、嘉禄(1225-26)の頃には「文室」と書くようになっていた。
※吹きしく→「吹き頻(しき)る しきりに吹く」と解したが、定家筆の天福本『後撰集』では「吹敷」と書いており、風が吹いたために落ちて地上に散り敷いたと解している。この解の場合、「吹敷」が「秋の野」を修飾し、それを再び「玉ぞ散りける」と見立てたことになり、説明的に過ぎるのではないか。
※貫きつめぬ玉→糸で貫いてとめていない玉。
◎瞬間的な景をみごとにとらえた歌となっている。
【参考1】
秋の野に置く白露を今朝見れば玉やしけるとおどろかれつつ (後撰集・秋中・309・忠岑)
秋の野に置く白露は玉なれや貫きかくる蜘蛛の糸すぢ (古今集・秋上・225・文屋朝康)
たまぼこの道も宿りもしら露に風の吹きしく小野の篠原 (壬二集・2464)
【参考2】
◎文屋朝康の歌
秋の野に置く白露は玉なれや貫きかくる蜘蛛の糸すぢ (古今集・秋上・225)
吹くからに秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ (古今集・秋上・225 定家本は文屋康秀の作とするが、平安期書写の本の多くは朝康の作とする。『百人一首』二三番)
浪分けて見るよしもがなわたつみの底のみるめも紅葉散るやと (後撰集・秋下・417)
【文屋朝康】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
生没年未詳。文室とも書く。文屋康秀の息子。天武天皇の孫の文室真人の末流。『古今集目録』に、寛平四年(892
)正月二十三日駿河掾に、延喜二年(902)二月二十三日、大舎人大充に任じられたとあること以外に伝記はわからない。寛平初年の『是貞親王家歌合』『寛平御時后宮歌合』に歌をよんでいることからみても、当時、歌人として相当に重んじられていたらしい。『古今集』に一首、『後撰集』に二首入集しているのが、知られる歌のすべてである。
三八 忘らるる身をば思はずちかひてし人の命の惜しくもあるかな 右近(うこん)
【出典】
『拾遺和歌集』恋四・870
(題しらず) 右近
忘らるる身をば思はず 誓ひてし人の命の惜しくもあるかな
【現代語訳】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
忘れられてしまう私の身のことは、何とも思いません。ただあれほど神前にお誓いになったあなたのお命が、いかがかと惜しまれてならないのです。
【鑑賞】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
かたく神仏に誓ってまで契りをした人から忘れられてゆく恋の破綻を、相手を恨むのではなく、かえってその人が神罰にほろびゆくことを惜しく思うといった、女の恋心の悲しさがよく出ている歌として、いかにも定家が晩年に好んだ恋歌の典型といえる。『大和物語』に歌物語が見られることや、『源氏物語』の明石の巻に、この歌をふまえた描写があることも、いっそう定家の心をひきつけたことと思われる。「被忘恋」の題で、「身を捨てて人の命を惜しむともありしちかひのおぼえやはせん」(拾遺愚草・中)という全くこの歌によりかかった歌をよんだり、『八代集秀逸』に選び入れていることなどからも、高く評価していたことが知られるのである。
【語釈】
※忘らるる身→相手に忘れられる我が身。この「忘る」は四段活用。「るる」は受身の助動詞「る」の連体形。「身」に続く。「身」は「我が身」のこと。
※誓ひてし→「誓ふ」は神の前で誓言すること。「住吉のあら人神に誓ひても忘るる君が心とぞ聞く」参照。「てし」は完了の助動詞「つ」の連用形に、過去の助動詞「き」の連体形が接続したもの。
【参考】
『大和物語』第八十一段〜第八十五段
※『大和物語』→950年代に成立した歌物語。『伊勢物語』に対する『大和物語』。
人々が語っていた風刺を纏めたもの。
八十一
季縄(すゑなは)の少将のむすめ右近、故后(きさい)の宮にさぶらひけるころ、故権中納言の君おはしける、頼めたまふことなどありけるを、宮にまゐること絶えて、里にありけるに、さらにとひたまはざりけり。内わたりの人来たりけるに、「いかにぞ、まゐりたまふや」と、問ひければ、「つねにさぶらひたまふ」といひければ、御文奉りける。
忘れじと頼めし人はありと聞くいひし言の葉いづちいにけむ
となむありける。
※右近→男性と対等に付き合っていた。
※頼めたまふことなどありけるを→下二段活用動詞連用形、自分が期待せず相手に期待させる。
※頼めし人→頼りにさせた人。
※あり→健在である。
※女房と貴公子はその場限りの恋であった。その恨みの歌。
八十二
おなじ女のもとに、さらに音もせで、雉をなむおこせたまへりける。返りごとに、
栗駒の山に朝たつ雉よりもかりにはあはじと思ひしものを
となむいひやりける。
※雉→かりそめの対象。
八十三
おなじ女、内の曹司にすみける時、しのびて通ひたまふ人ありけり。頭なりければ、殿上につねにありけり。雨の降る夜、曹司の蔀のつらに立ち寄りたまへりけるも知らず、雨のもりければ、むしろをひきかへすとて、
思ふ人雨と降りくるものならばわがもる床はかへさざらまし
となむうちいひければ、あはれと聞きて、ふとはひ入りたまひにけり。
※内の曹司→個室。待遇の良い女房。
※頭→今の内閣官房長官。
※わがもる→「もる」は「雨が漏る」と「守る」の掛詞。
※うちいひければ→「うち」は小さな、軽く。
※ふとはい入り→「ふと」は急に。「はひ入り」は這うようにして。
八十四
おなじ女、男の「忘れじ」と、よろづのことをかけてちかひけれど、忘れにけるのちにいひやりける。
忘らるる身をば思はずちかひてし人のいのちの惜しくもあるかな
返しは、え聞かず。
※おなじ女→右近。
※男→相手の男は解らない。
※「忘れじ」→「じ」は打消しの意思。
※え聞かず→情報を仕入れた人が返しまで聞いていない。情報を提供した人から聞いていない。
八十五
おなじ右近、「桃園の宰相の君なむすみたまふ」などいひののしりけれど、虚言なりければ、かの君によみて奉りけり。
よし思へ海人のひろはぬうつせ貝むなしき名をば立つべしや君
となむありける。
※すみたまふ→一緒に住む。
※うつせ貝→空の貝。
【右近】 (新版百人一首 島津忠夫=注釈 角川ソフィア文庫による)
生没年未詳。右近衛少将季縄(片野の少将とよばれた人。鷹匠。勅撰歌人)の娘。醍醐天皇の皇后穏子(おだいこ、おだやけきこ)の女房として、村上期歌壇で歌人としての名があり、『天徳歌合』、『応和二年内裏歌合』、康保三年の『内裏前裁合』に方人、歌人として加わっている。元良親王・藤原敦忠・師輔・朝忠、および源順・清原元輔・大中臣能宣らと交際のあったことが、歌の詞書や『大和物語』順らの家集から知られる。『後撰集』に五首、『拾遺集』に三首、『新勅撰集』に一首入集。
男性と対等に向かいあった才女。